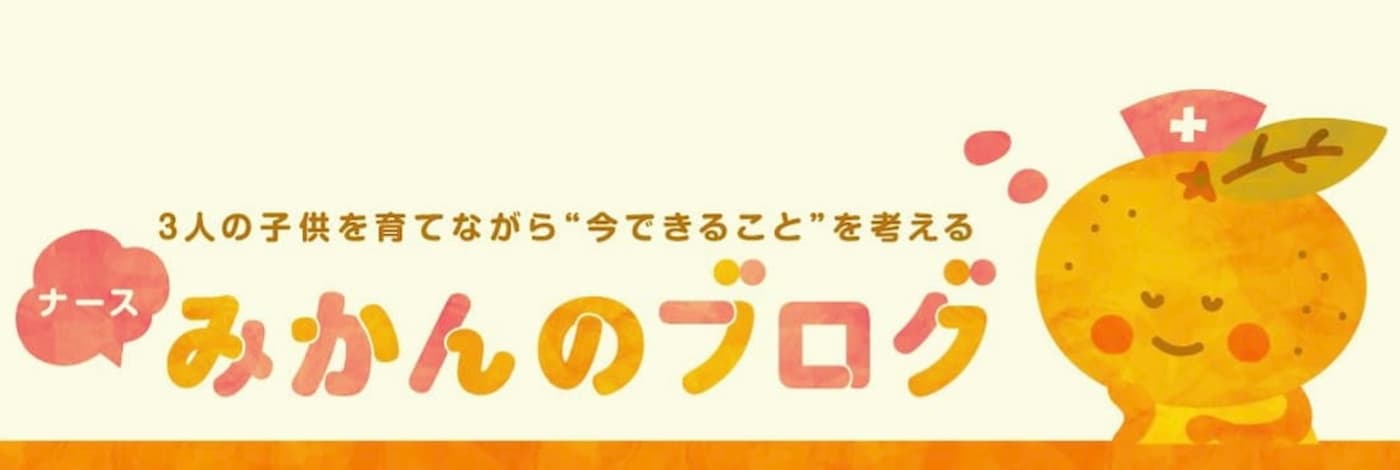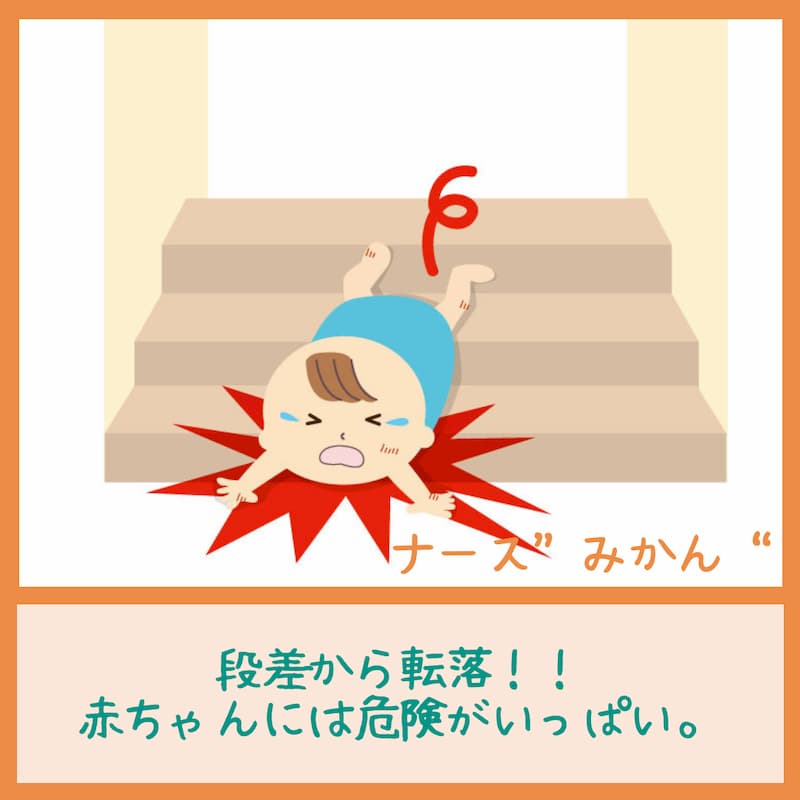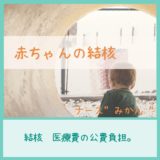この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
赤ちゃんって『昨日できなかったのに今日できるようになる』ってことがたくさんあります。
うつ伏せになれるようになって、寝返りができるようになって、ハイハイができるようになって…
 みかん
みかん
そんな成長の中で気を付けないと行けないのが転落です!
 みかん
みかん
こんな私も赤ちゃんの転落でヒヤヒヤした経験が一度や二度ならず💦
気を付けているつもりでも、ほんの一瞬の隙に…なんてこともあるんです。
今回はそんな赤ちゃんが転落したときの対処方法や転落させないための予防策について書いていきますね。
転落した場合の対処方法
転落した場合どうすればいいのかってことを知っておいて欲しいので、最初に対処法を書いていきますね。
転落してしまったら、まずはなんといっても赤ちゃんの状態を観察しないといけません。
赤ちゃんは頭の比重が重いので、転落するとどうしても頭を打ってしまう確率が高くなります。
頭は生死に直結する問題にもなりうるので怖いですよね。
救急搬送しなければいけない場合の症状を先にまとめておきます。
こんな場合は迷わず救急搬送

次のような症状が一つでもあれば救急搬送してください。
- 意識がない
- けいれんしている
- 視線が合わない
- 何度も嘔吐する
- 大量の出血がある
- 直接当たっていないのに耳や鼻からの出血がある
上記のような症状が見られれば急を要する場合が多いので119番を押してください。
意識があるかどうか確認する
「すぐ泣いたら大丈夫」「たんこぶができてたら大丈夫」って聞いたことがありませんか?
 みかん
みかん
多くはその通りです!
脳への影響が少ないので、すぐ泣くことができて、たんこぶができていることで頭の中の出血の可能性が低いって考えるわけです。
でも逆の場合「すぐ泣かなかったら?」「たんこぶがなかったら?」って不安になりますよね。
一概に全てが当てはまる訳ではありませんので、落ち着いて赤ちゃんの変化を見逃さないようにすることが大事になります。
特に転落後24時間はよく赤ちゃんの様子を見ていてくださいね。
脳内でジワジワと出血していて、症状が出てくるのが遅い場合があります。
※転落直後に受診していても、脳内の出血はCT画像ではすぐに写りません。受診時に説明はされると思いますが、赤ちゃんの変化を見逃さないことが大事になります。
- 呼び掛けに反応があるか
- 視線が合うか
- ぐったりしていないか
などを注意深くみてくださいね。
外傷があるかどうか確認する
明らかに出血があったり、腕や足の向きがおかしいなどの症状があれば受診してください。
出血が多いようであれば、救急搬送をしてくださいね。
救急車がくるまでの間、できそうであれば出血部位を清潔な布で押さえたり、出血部位を心臓よりも高い位置になるようにすることで、出血量が抑えられます。
少量の出血であれば、家庭内でできる消毒や絆創膏で対応できるかと思います。
あと、たんこぶ(内出血)があれば早急に冷やすことで、たんこぶが大きくなるのを抑えることができます。
打ったことに気づいたらできるだけ早く冷やすようにしてくださいね。
できれば10分以上冷やすことをオススメしますが、くれぐれも低温やけどに注意しながら時々は冷やしている部位を確認してくださいね。
骨折や脱臼をしていないか確認する
骨折や脱臼は明らかに、腕や足の向きがおかしい場合なんかはわかりますが、見た目では分かりにくい場合もあります。
赤ちゃんの様子を観察しながら、さわると痛がったり、全く動かさなかったり、また足や腕なら左右の長さが違っていなかなども見ておきましょう。
何度も嘔吐やえづいたりしていないか確認する
転落した恐怖や痛さから大泣きすると、刺激で嘔吐してしまうことがあります。
ただし、それは泣き止めば治まる症状です。
時間がたっても何度も嘔吐していたり、えずいたりするようであれば脳内で何か起こっている可能性があるので受診してくださいね。
受診をするか迷ったときは…

小児救急電話相談っていうものを聞いたことがありませんか?
母子手帳の後ろの方のページにも書いてあるんですが、電話で状況を説明すると受診するかどうかの相談や対応についてのアドバイスがもらえます。
小児救急電話相談事業
#8000
※携帯電話・NTTのプッシュ回線以外の場合は都道府県によって固定電話の番号があります。
小児科医の支援体制のもと看護師が相談に応じてくれます。
私が実際に電話したときも受診が必要かどうか相談に乗ってもらえ、受診可能な病院を数件教えてくださいました。
ただし都道府県によって電話のかけられる時間帯が違って、多くは夜間のみの電話対応になります。
急を要する場合は、もちろん電話相談ではなく119番で救急車を呼んでください。
転落予防
ここからは転落しないように、またもし転落しても大きな事故になる可能性が低くなるようにできることを書いていきます。
目を離さない
まずはなんと言っても目を離さないようにすることが一番です。
でも赤ちゃんが動けるようなってくると、思いもよらぬことが起きるんです。
もちろん見ているつもりでも数秒目線を逸らしたら危険な状態だったなんてこともあります。
なので、できるだけ手の届く範囲にいて、見逃さないようにすることが大事になります。
ベビーグッズは使用方法を守る
ベビーベッドでは必ず柵をしたり、ベビーチェアーもベルトをするなどの使用方法を守るようにしてくださいね。
忙しかったり、子どもがいやがったり、慣れてくると怠ってしまうこともあるかもしれませんが、側にいるとき以外は必ず“安全”のために確認してほしいと思います。
危険を予知する

あらかじめどんな危険がありそうか考え対策していきます。
赤ちゃんは歩きはじめは絶対に転ぶものだし、赤ちゃんには危険予知はできないので、大人が考えて先手を打つ必要があります。
月齢や、転落の仕方(前だけじゃなく、頭の重みで後ろへドーンと転落することも多々あります)、いろんなことを踏まえて生活スペースに危険がないか考えてみましょう。
- 段差がないか。
- 家具などの配置は?
- 転んだ時にどこにぶつかりそうか。
そして、赤ちゃんの動きを1歩先まで考えて対策をしましょう。
たとえば、寝返りが出来ていなくても寝返りで転落する危険のある所には寝かせない、立ち上がれないと思っていても立ち上がると届く範囲に危険なものは置かないなどです。
転落予防グッズ
ここからは転落予防に役立つグッズを紹介していきます。
赤ちゃんが動き始める時期に必須なのが柵です。
特に階段のある家は危ないので柵を使って安全に過ごせる環境を整えてあげてくださいね。
キッチン周りなどの危険な場所へ行かないようにするベビーゲートもありますが、階段で使用できるタイプは安全性を考慮して片側にしか開かないようになっています。
間違えて両開き可能タイプを取り付けてしまうと危険なので気を付けてくださいね。
あとは転落したときの吸収を和らげるならジョイントマットがオススメです。
はいはいの時期の膝にもやさしいし、子どもの遊ぶスペースにもいいですよね。
転落予防のグッズ以外にも、テーブルの角をガードするものや、赤ちゃんが安全に生活するためのグッズがたくさんあるので各家庭に合わせて購入を検討してみてくださいね。
みかんの一言
大きい声では言えませんが、第1子をベビーカーから落としたことがあって(肩ベルトが壊れていて、腰しかベルトをしていませんでした)、
第2子もベビーベッドから落としたことがあります。(寝返りができない時期に大丈夫だろうと柵をしていなかったら、足で体をズリズリ斜めにして頭から落ちてきました)。
第3子も、旦那が一瞬目を離した隙にソファーから落ちました。
 みかん
みかん
 みかん
みかん
こけたり頭を打ったりは完全には防ぐのは難しいのですが、防げることもたくさんあります。
正直、赤ちゃんの寝ている時間以外は気の休まる暇はありません。
と言っても寝ていると思ってたら起きてることもあるので、昼寝でもかなりこまめに見ておかないといけないんですけどね。
だからといって転落させてしまったら、言い訳できることじゃないのは確かですよね。
対処方法を知って、転落予防グッズも上手に取り入れながら、家族で協力して赤ちゃんを危険から守っていきましょうね。