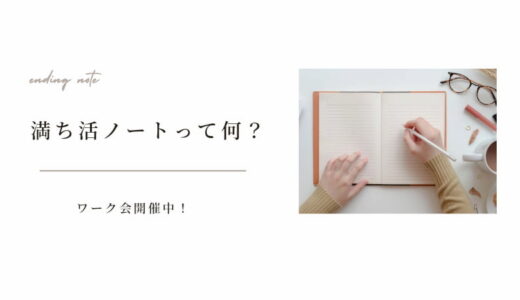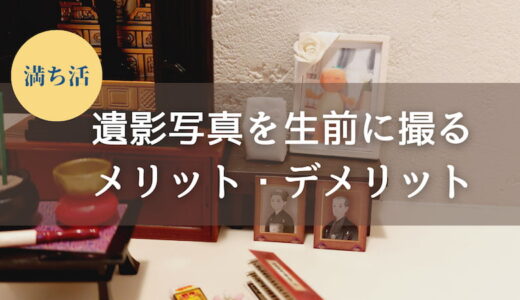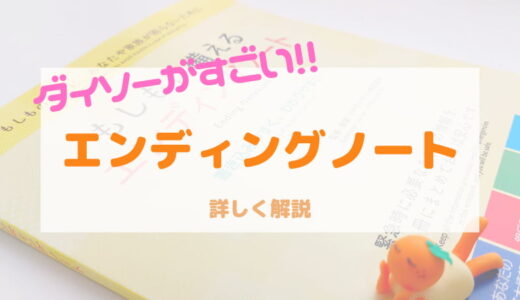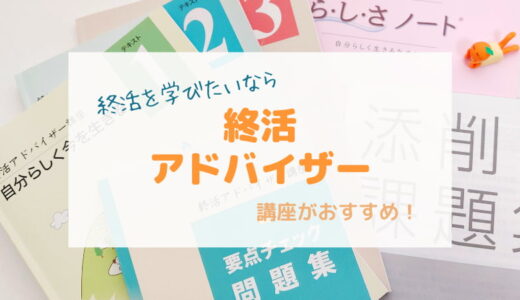この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
誰しも限られた時間を有意義に使いたいと考えていると思います。
私も時間管理をするためにアレコレ書き出してみたり、やりたいことリストを上げ計画を立てたりしていました。
なのに一向に時間をうまく使えたと感じることができなかったんです。
 みかん
みかん
比較してもどうしようもありませんが、自分だけが時間を無駄に過ごしてる気がして自己嫌悪に陥ることもあったんですよね。
がんばってるつもりだけど、なんだかんだで忙しい。
できないのは時間が足りないからだ…なんていう誰でもない時間のせいにしてしまうことも。
たくさん本も読みましたが、成功者が語る時間管理の方法はいずれも細かく計画を立てたりとにかく行動する話ばかり。
ですが、この本を読んでその考えが180度変わりました。
この記事では時間の使い方が下手だと感じている人に読んでもらいたい1冊として『限りある時間の使い方』をご紹介していきます。
[itemlink post_id=”769″]
この記事でわかること
- 『限りある時間の使い方』の要約
- 『限りある時間の使い方』を読んで実際に行動に移せそうなこと
- 時間に限りがあると意識するためにすること

みかん
終末期医療に携わり300人以上の方の看取りに立ち会ってきた看護師です。病棟や外来化学療法室、特養などで死を見つめた多くの方と関わってきました。 終活をポジティブなイメージに変えるべく『満ち活』として最期の時を意識しながら今を大切に生きることを発信中。
限りある時間の使い方 要約

時間の使い方についてどんなことが書いてある本なのか気になっていると思うので最初に『限りある時間の使い方』を要約します。
この本は大きくは2部に分かれているので、構成に沿ってお伝えしますね。
※本書の意図とズレないよう細心の注意を払って書きますが、個々の解釈の違いもあることをご了承ください。
 みかん
みかん
part1.現実を直視する
part1.では、なぜいつも時間に追われるのかなどの、時間に対するこれまでの考え方を再認識する内容が書かれています。
- 時間は本来「使うモノ」ではなく生活が繰り広げられる舞台
- 時間の有効活用ばかり気にして今を見失っていないか
- 現実を直視する=できないことはできないと認める
- タスクを上手に減らす3つの原則
- 自分は万能ではないと受け入れる
本書では、はじめに時計の無かった時代と現代の比較しています。
昔の人たちは生活をする上で農作業に時間を割いたり便利なモノが少ない上に、寿命が今よりも短かいですよね。
私たちよりも明らかに時間が少ないはずなのに「時間が足りない」と思っていなかった点について考察しています。
- 農作業や日常生活は繰り返し行うことばかりで、すべてを完了した状態がというのがありえないため急いだり競争したりする必要がなかった
- その時期に必要な種を植えたり実を採ったりということをして生活リズムを付けていたので時間という概念がなくても生活できていた
でも数人以上で仕事をするとなると状況が変わります。
わかりやすく皆が合意できるということで時計の登場です。
時計という目に見える形で他者と比較管理するツールができたことで、労働時間など様々な面から時間管理をすることが求められるようになります。
そして決められた時間に働いたり効率化を意識して行動し始めることになります。
いつの間にか時間はどんどん生活から切り離され使うモノとして認識されるようになっていきます。
本文に下記の言葉があります。
時間を「使う」ようになった僕たちは、「時間をうまく使わなければ」というプレッシャーにさらされる。
引用:p33
まさに、時間を「無駄」にすると罪悪感が芽生え、やることが多すぎると時間の使い方を改善しようと効率的に働く方法を模索する人が増えました。
そして同時に2つのことをやるマルチタスクの誘惑にハマっていくことになります。
家事をしながら動画視聴、テレビを見ながら仕事(宿題)、子どもを見ながらSNSなど日常的に同時進行で複数やっていることが多いですよね。
すべてが悪いわけじゃありませんが、時間を有効に使っている気になっている、そしてどちらも完了させたいと思っているとしたらしんどくなります。
時間の有効活用ばかりを考えていると、人生は想像上の未来に描きこまれた設計図となり、ものごとが思い通りに進まないと強い不安を感じるようになる。そして時間をうまく使えるかどうかが、自分という人間の価値に直結してくる。
…どんなに必死で頑張っても、まだ足りない気がする。もっと早く、もっとたくさんやらなければ気がすまない。
…いつかタスクがすっかり片付いたら、そのときこそリラックスして楽しもう、というわけだ。
引用:p33-34
一見、自分にタスクを課すことは未来に向けてがんばっているから良いことのように思うかもしれませんが、問題は未来のことしか考えられなくなることです。
現代人はなぜか時間をコントロールしようと多くのタスクを自分に課したりしがちですが、そもそも時間をコントロールしようとする考えが人生の難易度を極端に上げてしまっていると著者は伝えています。
言い換えると今を生きることができなくなってしまうことが問題なのです。
やることリストの項目を一つずつ消していくことに達成感を感じたとしても、今やっていることは今しかできないことの最優先事項なのかと問うてみてください。
本文ではタイムマネジメントついてこのように触れています。
みんな何らかの現実を直視するのが怖くて、それを避けるために生産性やタイムマネジメントにしがみついているのではないか、ということだ。
引用:p39
仕事を全部こなして、副業もして、いつかお金などの不安から解放される期待をしている裏には、パートナーとの未来や子供との生活という無意識のうちに目を背けてしまっている何かがあるのではないでしょうか……。
恋愛や仕事、親や子供、病気や老後など、考えればキリがない程悩みの種は存在します。
無意識のうちに考えないように、もしくは後で考ようと先送りにしていませんか?
典型的な例を2つ上げてみますね。
- 何となく不調を感じつつも仕事が落ちついたら病院に行こう……手遅れだった
- 長期休暇が出来たら実家に帰ろう……親の最後に会えなかった
- もっとお金が溜まったら家族で旅行に行きたい……子どもには子どもの予定ができ一緒に過ごす時間がない
こんな話はよく聞きますよね。
また何かに挑戦して失敗するのが怖いからと先延ばしにしてしまうこともよくあります。
若い人にありがちな「本気を出せばできる」と思いつづけることで、怖いことから目をそらすことも現実を直視できていない一例です。
でも、逃げても事態が好転することはありません。
個々に悩みや不安の対象は違っても、この人生しかないということは皆同じです。
筆者は下記のように述べています。
現実を直視することは、ほかの何よりも効果的な時間管理術だ。
引用:p42
要するにできないことはできないと認める・受け入れることが大事だということです。
アレもコレもと思うかもしれませんが、本当に全部自分にとって必要なことか今一度考え直してみてください。
できないことを認めることで、その時間をできることに使えるというのは人生においてとても大きなことです。
そしてこんなことも書かれています。
限りある時間、という現実からそらす方法として、おそらくもっとも魅力的なのは、複数のプロジェクトを同時に進めることだ。
p93
たくさんのタスクを自分に課すことで一つのことに全集中できない言い訳を作り、やった気にだけなるという最悪のシナリオです。
どうでもいい、誰でもできそうなタスクをこなして達成感を得ても、不安は拭えないですよね。
タスク管理の方法として、タスクを上手に減らす3つの原則が上げられています。
- まず自分の取り分をとっておく
- 「進行中」の仕事を制限する
- 優先度「中」を捨てる
詳細は本を読んでもらえればと思いますが、印象に残るフレーズは③の優先度「中」を捨てるということです
そこそこ面白い仕事のチャンスや、まあまあ楽しい友人関係。それを切り捨てるには惜しいように思えるけれど、限られた人生の時間を一番食いつぶしている可能性がある。
p96
本当に大事なこと以外に多くの時間を費やしていることにハッとしませんか?
私にはこの、そこそことかまあまあという自分にとって良さそうなことが何とも重大な落とし穴なんじゃないという気がしました。
人は後戻りできない状況に置かれた方が、選択肢があるときよりも幸せになれるというデータがある。
手持ちのカードを残しておくよりも、「これしかない」という状況の方が満足度が高まるのだ。
p107
できるだけ選択肢を少ない状態にするには優先度「中」を捨てるのは効果的です。
本当に大事なモノだけを見極めるという意味でも私たちは多くのモノを捨てる必要があるのだと感じました。
時間をコントロールしようとしたり、時間管理ツールでみっちり予定を立てることで何となくうまく人生を進んでいるような気がしていたら要注意ですね。
そして最後はこう締めくくっています。
「現実は思い通りにならない」ということを本当に理解したとき、現実のさまざまな制約は、いつのまにか苦にならなくなっているはずだ。
p132
※上記以外にもSNSについてや良い先延ばしについて、また、なぜやりたいことをやりたくないのかという話題にも触れています。
part2.幻想を手放す
part2.では人生の一回性を直視し、計画の捉え方や何をするべきかを考察しています。
- 人生には「今」しか存在しない
- 自分はここにいるという事実に気づく
- 自分にできることをする
今「未来のために」って頑張っていませんか?
資格をとるためや、目先にゴールがある未来のために頑張るのは良いことだと思います。
ですが、漠然と将来働かなくても生活できるように、老後に世界を旅したいからという遠い未来ばかりを目標にしていると危険です。
人生の「本当の意味」が未来にあると信じることで、今この時を生きることから逃げているわけだ。
p159
未来は今よりずっと良いことがあるという幻想のためにがむしゃらに頑張っても、それはいつまでたっても今ではなく未来にです。
ということは永遠に自分が満足する今がないということになりますよね。
そのために子育ての貴重な時間を仕事に費やしてしまったり、健康な体で旅行に行く機会を失ってしまったりする可能性があるのです。
今は今しかないのに……です。
計画を立てたり未来を見据えることが悪いというわけではなく、未来に固執しすぎることで未来の不安も今に襲い掛かることになり余計に生きづらくなります。
もし未来にばかり目を向けている自分が居たら、ここで行動を考え直してみるのが最善の選択!
今を生きるのはそう簡単でないと筆者は述べていますが、そのための考えも教えてくれています。
今を生きるための最善のアプローチは、今に集中しようと努力することではない。
p164
むしろ「自分は今ここにいる」という事実に気づくことだ。
あえて今という時間に集中するのではなく、この瞬間に自分が含まれているということを受け入れるための気づきです。
意識すると今に集中したくなってしまいますが、そうなるとまた時間と自分を切り離して考えることにつながるので、自然に受け入れるられるようにサラッと行きたいですね。
そして自分ができないことを認めて、できることに注力することが大切になります。
自分の無力さを認めて、不可能を可能にしようとする無駄な試みを放棄したとき、人は実際に可能なことに取り組むことができる。
p200
どんなに頑張っても必要な時間がかかるのは仕方ないし、急いでも不安が減るわけではありません。
なぜ現代人は本を読めないのかという問題も、時間がかかることに不満を抱いているからだと書かれています。
必要な時間は必要!と割り切る。そしてできることをする。
できることに力を注ぐというのは、最も有効な時間の使い方ですよね。
時間について自分でコントロールできる自分優位なものだと感じていたあなたも、もう時間はコントロールできないものだと気づいているはずです。
時間を支配しようとする態度こそ、僕たちが時間に苦しめられる原因である。
p248
時間に対する概念が変わることで、今まで感じていた不安や苦しさはなくなります。
あらゆることが自分の望むスピードで動かなくても、時間を支配しようとしていることにさえ気づくことができれば大丈夫!
時間をうまく使ったといえる唯一の基準は、自分に与えられた時間をしっかりと生き、限られた時間と能力のなかでやれることをやったかどうかだ。
p265
今ここからの時間をどう考え、どう使うかはあなた次第です。
このpart.2では、人生を生きはじめるための5つの質問も用意されています。
- 生活や仕事の中で、ちょっとした不快に耐えるのがいやで、楽な方に逃げている部分はないか?
- 達成不可能なほど高い基準で自分の生産性やパフォーマンスを判断していないか?
- ありのままの自分ではなく「あるべき自分」に縛られているのは、どんな部分だろうか?
- まだ自信がないからと、尻込みしている分野は何か?
- 若も行動の結果を気にしなくてよかったら、どんなふうに日々を過ごしたいか?
ぞれぞれの質問に対しての著者のアドバイスが本書には散りばめられていますよ。
[itemlink post_id=”769″]
付録 有限性を受け入れるための10のツール
この本の最後は有限性を受け入れるための10のツールが書かれています。
ツールのお題のみですが書き残しておきますね。
- 「解放」と「固定」のリストを作る
- 先延ばし状態に耐える
- 失敗すべきことを決める
- できなかったことではなく、できたことを意識する
- 配慮の対象を絞り込む
- 退屈で、機能の少ないデバイスを使う
- ありふれたものに新しさを見いだす
- 人間関係に好奇心を取り入れる
- 親切の反射神経を身につける
- 何もしない練習をする
※著書にはそれぞれの説明とアドバイスが書かれています。
【実践】3個の行動ポイント

ここからは実践できる行動ポイントをまとめていきます。
本の概要ポイントからわかることも多いですが、私が実際に行ったことも含めて書いていきますね。
- 終わりがくることを受け入れる
- もうすでに自分の人生を生きていることに気づく
- 手持ちのカードを減らし、自分にできることをする
終わりがくることを受け入れる
人は必ずいつかこの世を去ります。例外なく必ずです。
そんなことはわかり切っているはずなのに、私自身も時間が限りのあるモノだと直視できずに永遠といろんなことを先延ばしにしてしまっていました。
part1.で書かれている現実を直視できないです。
仕事が落ち着いたら子どもたちとの時間を作ろう、副業が成功したら家族で旅行に行こう、と未来にばかり楽しい希望を見据えて、実際のところそれはいつになったら実現するのか疑問が生じました。
今しかない子どもたちとのかけがえのない時間を「仕事が…お金が…」と言い訳ばかりしてしっかり向き合えていなかったと強烈に反省。
毎日毎日、家事・育児に追われて無意識のうちにいつまでもそれが当たり前に続くものだと錯覚していたんですよね。
この未来への先送りの中には自分が明日死ぬかもしれないという不安を霞める要素も間違いなく入っています。
人は必ずこの世を去るということは看護師という仕事柄、人一倍理解している気でいました。
なのに知らず知らずのうちに目を逸らし「あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ」と不安と焦りを勝手に増強させていたんです。
本文中に下記の言葉があります。
死を受け入れて生きる態度をいくらかでも取り入れることができたなら、現実は一変するということだ。
p82
この文章を見て、しっかり死を受け入れようという気持ちになりました。
まだ完全に不安や焦りがなくなったわけではありませんが、抗っても何をしても絶対に終わりは来るんだから今を楽しもうと思えるようになったんです。
子どもたちが一日に何度も呼ぶ「ママ」の声が苦にならなくなり、今この瞬間が大事だという感情が少しづつ増えてきました。
もし、明日が最後の日になるとわかっていたなら、仕事を優先することも子どもたちの話を遮って家事をすることも止めるでしょう。
老後穏やかに過ごしたいという目標は、子どもが一緒にいる今を楽しみたいに変わり、未来のために働くのではなく今できる範囲で無理なく働くことが私にとって正しい選択のような気がしています。
どんな時間を過ごしても終わりは必ずくるのです。
もうすでに自分の人生を生きていることに気づく
自分の人生が始まって40年以上経っていますが、まだ未来を夢見ているんですよね。
幼少期に、いつ亡くなるかわからない寝たきりの祖父にかわいがってもらい、父のDVという山を越え、看護師といういばらの道を進み、人一倍死を意識して生きてきたのに……です。
未来に良いことばかりを妄想していると、今に良いことがなくてもそこまで気にならなくなるんですよね。
だって未来が素敵なはずだから……。
一種の自己防衛本能とでも言うのでしょうか。未来が自分自身に安心感を与えてくれていたんです。
でも、生まれてからすでに40年以上経過しているのに全くもって今に満足できる体制が整っていないじゃないかという事実に気づきました。
もちろん未来も大切ですが、今も楽しんで未来も楽しめたらもっと素敵ですよね。
だったらやりたいことは今やってしまおうって思うようになったんです。
足腰弱って病院通いに生きがいを見つける前にもっとやりたいことがあります。
また、今書いているブログもそうですが「全力で頑張っても成功できないんじゃないか」という不安から、時には長時間ゲームをしてみたり、SNSに入り浸ってみたり、ただ動画を見るなんてこともありました。
自分のストレス発散のため…なんていう最もらしい理由を付けて自分を正当化していましたが、実際のところゲームをしてイライラすることもあれば時間を無駄にしてしまったと自己嫌悪に陥ることも多々ありました。
簡単で楽しいことをするのも気分転換には必要。
ですが気分転換の域を超えると罪悪感にしかなりません。
限りある時間の使い方を読んでからは気分転換という名の無駄な時間が目に見えて短くなったのは言うまでもありません。
今という時間はもう人生の真っただ中です。
手持ちのカードを減らし、自分にできることをする
あれもこれもというクセが付いてしまっているので、そこから手持ちをのカードを減らすのは至難の技です。
例えばこんなことをしていませんか?
週一のオンライン飲み会、月2回のゴルフ、仕事終わりや幼稚園送迎後の井戸端会議……。
これらはpart1のそこそこ・まあまあ楽しい出来事です。
私自身は上記のどれもしていないのに時間がないと感じていました。
どこに時間を使っているのか考えた結果、読書・ゲーム・マンガ・ブログ・書写・英語・ネットショッピング・終活……でるわでるわ極めもしない時間の過ごし方。
ここから手持ちのカードを絞らなければいけません。
優先順位は家族のこと(家事+一緒に過ごす時間)、そして終活のこの2つになりました。※身辺整理、終活ブログ含む
これはどう考えても私にしかできないことですからね。
残りは優先度「中」の一番時間を食いつぶしているというわれた項目に当てはまります。
実際のところ全部を捨てることはできていないのですが「やらなきゃ」という気持ちはなくなりました。
できなくてもいいんだと思うことで、焦りやイライラがなくなるだけでなく優先順位上位に時間を割くことができるようになったのは嬉しい成果です。
また、睡眠時間を削ってまで何かをすることもなくなったのも良き変化の一つです。
日々の体と心の安定は睡眠時間を確保することから始まると言っても過言ではありません。
※この話はココでは長くしませんが、睡眠は大事ですよ。
そしてグダグダ思い悩む時間があるなら行動してみようと思えるようになりました。
どうせいつまでたっても手探りで、確信のないままやるしかないのだから、尻込みしていても仕方ない。待つのはもう終わりだ。今すぐに、やりたいことをやりはじめよう。知識や技術が足りなくてもかまわない。
p261
結局のところ何となくずっと気になっている・迷っていることがあるならやってみようってことですよね。
自分の人生はいつ終わるかわかりません。
なのに〇〇が終わったらとか、準備が出来たらと言って渋るのも、未来のために仕事を頑張ると言って今をないがしろにすることも本末転倒。
何もかも片づいたあとの遠い未来に得られるかもしれない充実感ではなく、今ここにある人生をなんとかしなくてはならないという視点だ。
p236
切り捨てられることとやりたいことを明確にしたらあとは行動に移すだけですね。
今自分にできることに注力!!
まとめ 時間を上手く使いたければ終活をしてみよう!

人生には限りがあります。
死が確実にやってくること、そして自分が死に向かっていることを見つめたとき、人はようやく本当の意味で生きることを知るのだ。
p79
終わりを意識することで今が尊い時間だと実感することができます。
時間管理における死の意味は絶対です。
そこでちょっと意識してもらいたいのが終活!
まだまだ先と思いがちですが、果たして本当にまだまだ先のことでしょうか。
明日、明後日、1年後……どうなっているかなんて誰にもわかりません。
モノも情報もあふれて、息継ぎをすることすら難しくなってきた今だからこそ自分に大切なことだけを厳選し、ラクに生きることが求められている気がします。
限られた時間にできることは今を大事にすること。
過去に捕らわれすぎず、未来に思いをはせすぎず、『今』自分ができることの最優先事項に取り組む!
詰め込むだけの現実を手放して穏やかに自分の時間を生きるために。
もし、やりたいことができずに焦りや不安、苛立ち、永遠に終わらないタスクに縛られている人が周りにいたら、この本をおすすめしてみてくださいね。
限りある時間の使い方 書籍情報
[itemlink post_id=”769″]
- 2022年6月20日 第1刷発行
- 株式会社かんき出版
1975年生まれの47歳(2022年現在)
1994年にケンブリッジ大学卒業。
イギリスの全国紙の記者。
また、外国人記者クラブの若手ジャーナリスト賞などを受賞したライター。
心理学に関する週刊コラムが人気。
参考:限りある時間の使い方、ウェキペディア
1975年生まれの47歳(2022年現在)
翻訳家。
京都大学卒業後、ラインワール応用科学大学修士課程修了。
「限りある時間の使い方」以外に「エッセンシャル思考」「エフォートレス思考」「スタンフォード大学で一番人気の経済学入門」などの翻訳もされている。
参考:限りある時間の使い方
 みかん
みかん